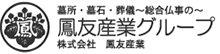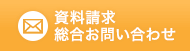スタッフコラム vol.05 <26年8月>
皆様 こんにちは。
今回は『ご焼香』についてお話してみたいと思います。
焼香の作法についてはご質問を受けることが多く、葬儀マナー本などにはひと通りのことは書いてあります。「何宗は何本線香を立てる」「何宗は何回お香をつまむ」等々。ただ、背景だとか意味合いだとかは、ほとんどの場合説明されていません。
そこで、少し詳しく書いてあるものを読むと、ご焼香の目的として
「心を落ち着かせる」
「心身を清める」
「御霊前・御仏前において敬虔な心を捧げる」
「仏様のお食事である」
「消臭効果がある」
概ねそのようなことが説明されています
つまり、辞書的に表現すると
「心と身体の穢れを祓い、清浄な心でお参りする際の作法。焼香によって醸し出される香りが「極楽浄土」を思い起こさせ、ご先祖様や亡くなられた方々が仏となり、私たちを見守り続けてくださることを実感する行為。従って仏となった方々を偲びながら焼香することが最高の供養。」
「仏様のお食事」説については、
「亡くなってから成仏するとされる四十九日の間、魂もわずかばかりの食事を摂る。もちろん我々の食事とは異なるが、粗飯ではなく、お香の煙を食する。」
「消臭効果」については、
 「仏教発祥の地インドはとても暑く、昔から臭いを和らげる、または香りを楽しむためのものとして焼香の習慣があり、中華大陸を経て仏教とともに伝来。日本は気候も文化も異なるため、日常的にお香を焚くことはあまりないが、仏教のお参りにおいて重要な所作として定着している。」
「仏教発祥の地インドはとても暑く、昔から臭いを和らげる、または香りを楽しむためのものとして焼香の習慣があり、中華大陸を経て仏教とともに伝来。日本は気候も文化も異なるため、日常的にお香を焚くことはあまりないが、仏教のお参りにおいて重要な所作として定着している。」
ちょっと小難しくなりましたが、実際は、消臭というよりも、香りによって心が落ち着き厳粛な気持ちになる、といった効果の方が高いかなと思います。
「亡くなられた方々のため」であると同時に「自分自身のため」にも焼香するわけです。
こうやって整理すると、なるほどと思いますし、ご焼香という行為にとても広がりが出てくるように感じます。(但し宗派によっては、亡くなられた方々に何かを手向けるという考え方はしないこともあります。)
ここまでは、いろんな人達の言葉を引用させていただきましたが、私自身がご焼香について普段感じていることもお伝えしたいと思います。
もちろん慣れ、不慣れがあったり、緊張からぎこちないこともあったりしますが、亡くなった方やご遺族に対し弔意を表す作法として、とても美しい形だと思います。
儀式において、やはり『形』は重要です。
「弔いたい」という気持ちがあっても、基本となる形がないと、その心を表現するのはとても難しいでしょう。逆に形にしっかり沿うからこそ、弔う気持ちの『芯』の部分をきちんと表現できるのだと思います。
ご焼香の作法は、何十年、何百年の積み重ねの中で出来上がったもので、だから、私たちにとって自然で綺麗なのだろうと思います。自然で綺麗なご焼香を行うには、見た目・姿勢などもあるでしょうが、「亡くなられた方々を想いながら、自分自身の心を落ち着かせ、身を浄める」ことを大切にしていれば十分ではないかと思います。